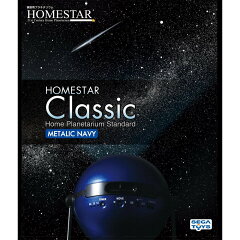1:共振応答とQ値の基礎理解
1.1 Q値とは何か?
Q値(Quality Factor)は、共振系の鋭さや選択性を示す無次元量であり、以下の式で定義されます:
また、減衰比 との関係は:
Q値が高いほど、共振ピークが鋭く、振動が長く続きます。
1.2 応答増幅率との関係
共振周波数付近では、入力振動に対する出力応答(Transmissibility)は Q値に一致します:
共振点(r = 1)では、となり、振幅が静的応答の Q倍に達します。
2:FEM解析における減衰モデルの比較
| 減衰モデル名 | 数式表現 | 特徴・適用範囲 | 主な出典 |
| レイリー減衰 | C = alphaM + betaK | 周波数依存性あり。低・高周波数で制御可能。 | ANSYS, NAFEMS |
| 複素剛性モデル | K* = K(1 + i*eta) | 材料固有の損失係数 eta を直接反映。中周波数帯に有効。 | JAXA JERG-2-310A, NASA TM |
| モード減衰モデル | zeta_n を設定 | 各モード個別に減衰を設定。精度高いが試験データが必要。 | NAFEMS, JAXA試験資料 |
| 等価粘性減衰 | Fd = c*x_dot | 単純なモデル。初期設計や教育用途に有効。 | Harris' Handbook, 機械力学教科書 |
※ANSYSでは、レイリー減衰と複素剛性の併用が可能。ANSYSやMSC Nastranでは、複数の減衰モデルを併用可能です。
3:Q値の設計限界と安全率の考え方
4:制振材の温度依存性と真空適合性の評価
4.1 温度依存性
-
高分子系制振材は、ガラス転移温度(Tg)付近で最大性能を発揮。
-
WLF式(WLF Equation) により、温度と周波数の換算が可能。
-
Master Curveを用いて広範囲の周波数帯で性能予測が可能。
4.2 真空適合性
宇宙空間では以下の特性が求められます:
-
アウトガス特性:TML < 1.0%、CVCM < 0.1%
-
低温耐性:-100℃以下でも柔軟性を維持
-
放射線耐性:フッ素系・シリコン系材料が有利
| 材料例 | Tg(目安) | 適用温度範囲 | 宇宙適合性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ビスコエラストマー | -10〜+20℃ | -40〜+80℃ | △(アウトガス対策必要) | 高損失係数だが制限あり |
| シリコンゴム | -50〜+150℃ | -100〜+200℃ | ◎(広く使用) | 放射線耐性も高い |
| フッ素系樹脂(FEP) | +80〜+120℃ | -100〜+250℃ | ◎(NASA推奨) | 光学機器周辺にも使用可 |
| EPDM | -40〜+120℃ | -60〜+150℃ | ○(用途限定) | コストパフォーマンス良好 |
5:宇宙機器に適した制振材の選定フロー
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 使用環境を確認する | 温度範囲、真空状態、放射線の有無など | 宇宙空間は -100℃以下になることも |
| ② 材料の候補を調べる | シリコンゴム、フッ素樹脂、ビスコエラストマーなど | 材料ごとに特性が違う |
| ③ 宇宙適合性をチェック | アウトガス、耐熱性、放射線耐性 | NASAやJAXAの基準を参考に |
| ④ 減衰性能を確認する | 損失係数(η)や減衰率(ζ)のデータを調べる | 振動をどれだけ吸収できるか |
| ⑤ 試験データで評価する | 材料を振動させて、応答を測定する | 実験で性能を確かめる |
6:実験データからQ値・減衰率を算出する方法
制振材の性能を調べるには、実際に材料を振動させて、どれだけ揺れが続くかを測定します。ここでは、共振試験(きょうしんしけん)という方法を使います。
測定の流れ
6.1. 材料を固定して振動させる
-
材料を台に取り付けて、振動試験機で揺らします。
-
周波数(振動の速さ)を少しずつ変えて、どの周波数で一番揺れるかを探します。
6.2. 共振周波数を見つける
-
一番大きく揺れた周波数を「共振周波数(きょうしんしゅうはすう)」と呼びます。
-
そのときの振幅(揺れの大きさ)を記録します。
6.3. 半値幅を測定する
-
共振周波数のピークから、振幅が約70%になる周波数を両側で探します。
-
その差を「半値幅(はんちはば)」と呼びます。
6.4. Q値を計算する
以下の式で計算できます:
または、
実験の補足
-
測定には加速度センサやレーザー変位計を使うことが多いです。
-
小野測器やIMV社などが、初心者向けの振動試験機を提供しています。
7:宇宙機器設計における減衰・増幅率設計の実践
7.1. 設計の基本方針
-
共振周波数の分散設計:構造モードが打上げ周波数帯に重ならないよう調整。
-
モード減衰比の設定:JAXAでは 0.005〜0.02 程度が推奨される。
-
制振材の選定:温度依存性・真空適合性・重量制約を考慮。
7.2. 解析手法
-
FEM+SEA統合解析:中高周波数帯の応答予測に有効(NAFEMS推奨)。
-
ジョイントアクセプタンス法:局所的な振動伝達の評価。
参考文献・技術資料一覧
-
Roark’s Formulas for Stress and Strain 構造応答と共振増幅率の理論式を網羅。設計者向けの定番資料。 https://jackson.engr.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/229/2023/03/Roarks-formulas-for-stress-and-strain.pdf
-
ASM Handbook Vol. 1, 5, 12 材料別の動的特性、損失係数、減衰率の実験値が豊富。CFRPやGFRPの積層方向による減衰変化も記載。
https://dl.asminternational.org/handbooks/pages/Handbooks_by_Volume
-
NASA SP-8050 (Interdisciplinary Design of Spacecraft) や NASA-HDBK-7005 (Dynamic Environmental Criteria) 宇宙機器の動的環境設計と振動試験の指針。 :
https://standards.nasa.gov/standard/NASA/NASA-HDBK-7005 -
MIL-HDBK-217F, MIL-HDBK-5J 電子部品や構造材の信頼性設計における減衰比の目安を記載。
https://www.rcj.or.jp/document/documen-1.html https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA295150.pdf
-
SPIE Optomechanical Design Handbook 光学機器の構造設計におけるQ値制御と制振材選定の実践ガイド。
-
JAXA JERG-2-310A (宇宙機構造設計標準) 宇宙機器の構造設計標準。モード減衰比の設定、荷重設定、強度評価基準を含む。
https://sma.jaxa.jp/TechDoc/index.php -
JAXA 熱真空試験ハンドブック 制振材の真空適合性評価、アウトガス基準、熱サイクル試験の設計指針。 https://sma.jaxa.jp/techdoc.html
-
小野測器 技術レポート 損失係数の測定方法、WLF式による温度依存性解析、Master Curveの構築手法。
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/newreport/damp/damp_9.htm
-
J-STAGE 宇宙機器の制振材設計 材料選定と温度・周波数依存性の実験報告。宇宙機器における制振材の実用性評価。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/souonseigyo1977/15/1/15_1_45/_pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsass/56/652/56_652_244/_pdf/-char/ja
-
国立情報学研究所 博士論文(CiNii) ERダンパの温度応答と制振性能の解析。粘弾性材料の温度依存性に関する詳細な実験。 https://cir.nii.ac.jp/crid/1871146592782977664
-
NAFEMS 振動解析ガイド FEM減衰モデルの比較と適用指針。モード減衰、複素剛性、周波数依存モデルの実務的解説。 https://www.nafems.org/publications/pubguide/list/
-
ANSYS Mechanical ユーザーガイド レイリー減衰・複素剛性モデルの実装方法、減衰パラメータの設定手順。
-
SpringerLink 材料力学論文群 CFRP・GFRPの損失係数と温度依存性、複合材の振動応答に関する研究論文。
-
https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071633048
- ESA 構造設計指針 欧州宇宙機関における制振材の選定基準、構造設計標準。
https://ecss.nl/standards/active-standards/
https://ecss.nl/hdbk/ecss-e-hb-32-20a-structural-materials-handbook/
- ECSS-E-HB-32-20A Structural materials handbook
- ECSS-E-ST-32-01C Rev.1 Mechanical Loads
- ECSS-E-ST-32-02C Structural Finite Element Models
- ECSS-E-ST-32-03C Structural Testing
- ECSS-E-ST-32-10C Structural Factors of Safety for Spaceflight Hardware
-
Granta Design 材料DB 損失係数・Tg・アウトガス特性などの材料物性データベース。ANSYSとの連携も可能。
https://www.ansys.com/ja-jp/products/materials/materials-data-library
- MIT OCW 構造力学講義資料 Q値と減衰率の導出、共振応答の理論解説。教育用に最適。
https://ocw.mit.edu/courses/1-051-structural-engineering-design-fall-2003/
https://ocw.mit.edu/courses/4-440-basic-structural-design-spring-2009/
https://ocw.mit.edu/courses/16-21-techniques-for-structural-analysis-and-design-spring-2005/
-
Harris' Shock and Vibration Handbook 振動・減衰理論の世界的標準。Q値、粘性減衰、実験手法の網羅的解説。
- ASTM E756 Standard Test Method for Measuring Vibration-Damping Properties of Materials 制振材の損失係数(η)を測定するための国際標準試験規格。
|
|
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=13273520&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6007%2F9784339046007.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f304ec2.c96634b9.4f304ec3.e96d8a34/?me_id=1262829&item_id=10073502&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fseijoishii%2Fcabinet%2Fitemimg1-66%2F63fdb08ecdb39.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21497533&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0652%2F9784295410652_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f31700f.ce92941d.4f317010.57600b94/?me_id=1230067&item_id=10002535&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffuji-shop%2Fcabinet%2Fkashi%2Fimgrc0091674232.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21688665&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7924%2F9784901867924_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f2cac34.c853a13e.4f2cac35.1aea3088/?me_id=1356830&item_id=10003284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexicoast02%2Fcabinet%2F12540646%2Fimgrc0110527156.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21784854&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8547%2F9784910558547_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f2cac34.c853a13e.4f2cac35.1aea3088/?me_id=1356830&item_id=10006906&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexicoast02%2Fcabinet%2F12540646%2Fimgrc0110526810.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21691022&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4117%2F9784759824117_1_13.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f5866da.49e3e3cb.4f5866db.e3fce52f/?me_id=1210297&item_id=10000187&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fohgiya-f%2Fcabinet%2Fef%2Fshohin%2Foyatu-c_kago.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
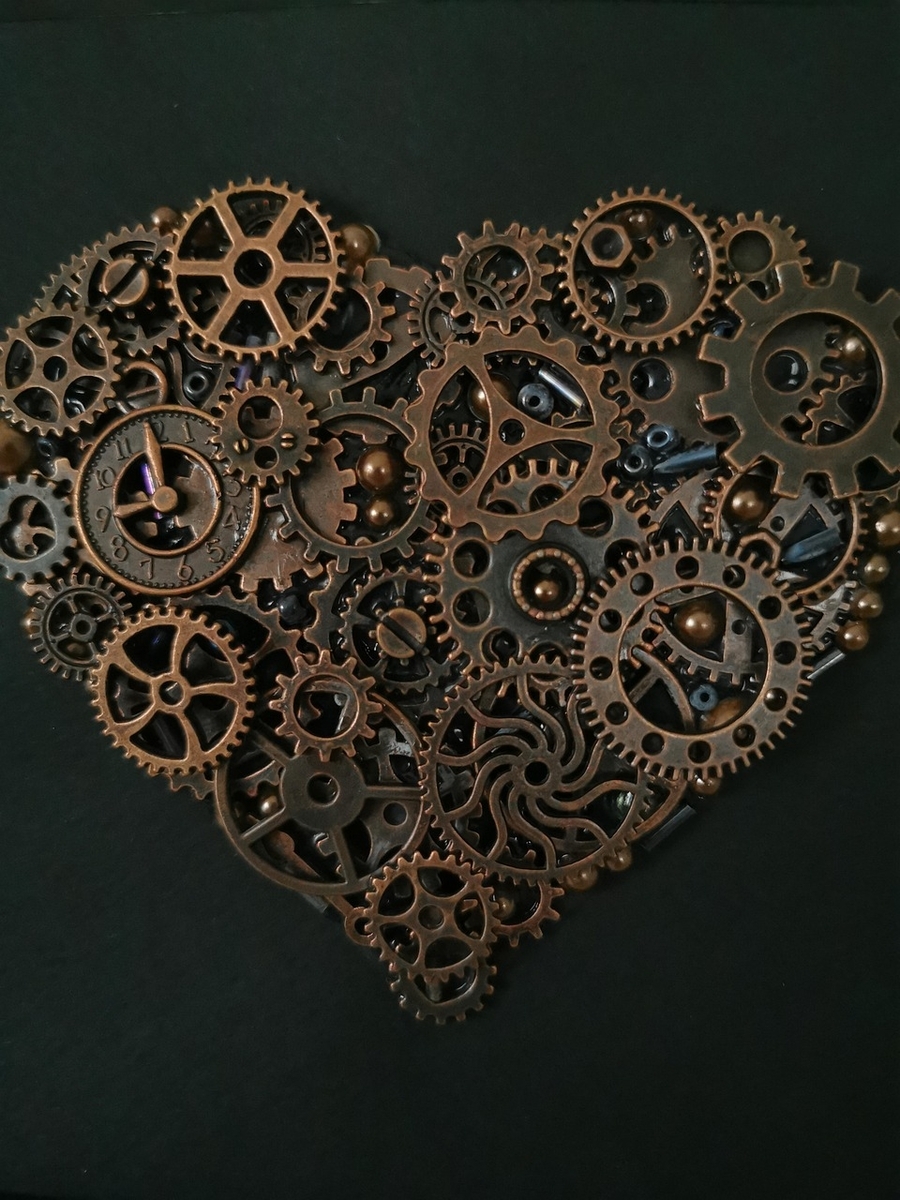
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=16982732&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1337%2F9784789841337.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f32aa16.b50faf40.4f32aa17.5f5764cc/?me_id=1307031&item_id=10000467&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fglobalgarden%2Fcabinet%2Fsyouhinpage%2Fnuts%2Fdai1armoundkurumi%2Falmondsu1kg-dai1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21710612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0578%2F9784766430578_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f314f8b.664b063d.4f314f8c.138217b2/?me_id=1427774&item_id=10000016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhuggyu%2Fcabinet%2F10942442%2Fkk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21689177&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2547%2F9784860592547_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f58377b.9432338c.4f58377c.12cd71b2/?me_id=1315222&item_id=10001406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdailymeg%2Fcabinet%2F04725073%2Ffree_1727796909176.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=20779186&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2316%2F9784339012316.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f32af93.3f76b0cc.4f32af94.a036a426/?me_id=1357996&item_id=10000173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdining-shioso%2Fcabinet%2Fmixnuts-4_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)