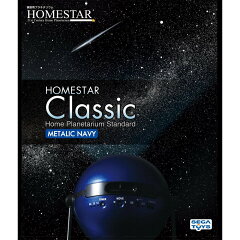1. 代表式
構造部材に切欠きや段差があると、荷重が局所的に集中し、名目応力を大きく超える応力が発生します。
この現象を定量的に評価するために使われるのが、応力集中係数 Kt(Stress Concentration Factor)です。
代表式は以下の通りです:
【設計用補正応力 Sigma_corr の算出】
ここで、 σmax:局所的に発生する最大応力 σnom:名目応力(荷重 ÷ 想定断面積)
技術的には、Kt は形状・寸法・材質・荷重条件によって大きく変化します。 特に、CAE解析では σmax がメッシュ依存で過大評価されることがあり、補正が不可欠です。
この考え方を直感的に伝えるなら、Kt は「力がどれだけ“狭い場所”に集中しているか」を表します。
例えば、同じ荷重でも広い面で支えれば応力は分散されますが、狭い点で支えると、そこに力が集中してしまいます。
設計者はこの“集中度”を数値で把握することで、摩耗・変形・破壊のリスクを事前に評価できます。
検索キーワード例 応力集中係数, stress concentration factor, Kt, σmax, σnom, notch effect, CAE補正, Peterson chart, DIN 743-2 local stress correction
2. Excelでの計算式と入力方法
| 計算内容 | Excel関数例 | 補足 |
|---|---|---|
| 名目応力 σnom | =F1/A1 |
F1:荷重[N]、A1:断面積[mm²] |
| 応力集中係数 Kt | =G1/F2 |
G1:CAEで得られた最大応力 σmax、F2:σnom |
| 補正応力 σcorr | =Kt*σ_nom |
Kt を用いた局所応力の補正値 |
| Peterson係数の参照 | =VLOOKUP(H1,Table_Kt,2,FALSE) |
H1:形状分類、Table_Kt:Kt係数表(Roark’s等) |
補足: Ktは形状・寸法・荷重方向によって変化するため、Roark’s Formulas や DIN 743-2 の係数表を参照し、Excelで自動補正できるようにしておくと設計レビューで有効です。
CAE解析結果の σmax はメッシュ依存性があるため、Kt による補正が必要になります。
3. 用語解説
-
応力集中係数(Kt):局所的な最大応力と名目応力の比率
-
取得方法:Roark’s Formulas、Peterson Chart、DIN 743-2、NASA RP-1228
-
-
名目応力(σnom):荷重を断面積で割った平均応力
-
取得方法:F ÷ A により算出。CAEでは全体応力場の基準値として使用
-
-
局所応力(σmax):CAE解析で得られる最大応力。メッシュ依存性が高い
-
取得方法:CAE結果から抽出。補正には Kt が必要
-
-
補正応力(σcorr):Kt を用いて名目応力を補正した値
-
取得方法:σcorr = Kt × σnom
-
-
Peterson係数:切欠き形状ごとの Kt 代表値。Roark’sやASM Handbookに収録
-
取得方法:係数表から参照。Excelで自動化可能
-
4. 視覚的理解のためのヒント集(Ktと局所応力)
4.1. 切欠きがあると応力が「集中」する理由
部材に段差や穴があると、応力の流れが乱れ、特定の点に力が集まります。 この集中度を数値化したのが Kt であり、設計者はこの値を把握することで破壊リスクを予測できます。
4.2. 形状によって Kt は大きく変わる
同じ断面積でも、丸穴・角穴・段差・軸肩などの形状によって Kt は2〜10倍以上変化します。 Roark’s やDIN 743-2の係数表を活用することで、設計初期段階から補正が可能です。
4.3. CAE解析結果の σmax は過信できない
メッシュが細かいほど σmax は高く出る傾向があり、設計判断には補正が必要です。 Kt を用いて σnom を補正することで、現実的な応力評価が可能になります。
4.4. 設計判断の流れを頭の中で整理する
Step 1:荷重 F と断面積 A を確認し、σnom を算出
Step 2:CAEで σmax を取得し、Kt を計算
Step 3:Roark’s や DIN 743-2から Kt を参照し、補正値を確認
Step 4:σcorr = Kt × σnom を算出し、設計限界と比較
この流れを設計レビューで共有することで、局所応力に関する意思決定が明確になります。
5. 設計判断への応用
-
CAEで得られた σmax をそのまま設計判断に使うのではなく、Ktによる補正を行うことで、過大評価を防ぐ
-
Kt を明示することで、局所応力の設計限界に対する妥当性を数値で説明できる
-
Peterson係数やDIN 743-2の代表値を設計テンプレートに組み込むことで、設計レビュー時の根拠提示が容易になる
-
Kt を用いた補正応力(σcorr)を設計資料に記載することで、CAEと手計算の整合性を確保できる
-
応力集中部の形状変更(R付け、面取り、段差緩和)によってKtを低減する設計戦略が可能になる
-
材料選定時には、Kt × σnom が降伏応力を超えないことを確認することで、破壊リスクを事前に排除できる
6. 実用例
-
🇺🇸 展開構造のヒンジ部設計
-
NASA RP-1228 (Statistical Analysis of Fatigue Data) や Peterson's Stress Concentration Factors に基づき、切欠き部のKtを補正。CAE結果と手計算の整合性を確保。
-
-
🇩🇪 DIN 509で規定された逃げ溝形状に対し、DIN 743-2 を用いて切欠き係数および応力集中を算出
-
Ktを形状別に規定。設計資料に直接記載可能な係数表を提供。
-
-
🇫🇷 光学ユニットの支持構造設計
-
CAEで得られた局所応力に対して、Ktを用いた補正を実施。DIN 743-2を参照。
-
-
🇺🇸 鋼構造梁の接合部設計
-
ボルト穴周辺の応力集中に対して、Roark’sのKt係数を適用し、設計限界を補正。
-
-
🇩🇪 衛星搭載部品の応力集中補正
-
CAE解析結果に対して、Ktを掛けた補正応力を設計限界と比較。
-
-
🇫🇷 航空機胴体の補強部材設計
-
Ktを用いたリブ断面の応力補正。DIN 743-2に準拠した設計レビューを実施。
-
-
🇺🇸 教材用梁設計演習
-
Ktの定義と補正法を学習。CAEと手計算の違いを比較。
-
-
🇩🇪 精密機構の切欠き最適化
-
Ktを最小化する形状設計。CAEとRoark’s係数を併用。
-
-
🇫🇷 展開機構の軸設計
-
Ktによる応力集中補正を設計レビューに反映。DIN 743-2を根拠に採用。
-
-
🇺🇸 宇宙構造物の接続部設計
-
MIL-HDBK-5Jに基づくKtの適用。CAEと手計算の整合性を確保。
-
7. 設計ミス・トラブル事例
-
🇺🇸 Ktを考慮せず、CAE結果のσmaxをそのまま設計判断に使用 局所破壊が発生。補正戦略が未実施。
-
🇩🇪 DIN 743-2の適用範囲を誤り、Ktを過小評価
-
軸肩部の応力集中が設計限界を超過。
-
-
🇫🇷 CAEメッシュが粗く、σmaxが過小評価され、Ktの補正が不十分
-
設計限界を逸脱し、現場で補強が必要に。
-
-
🇺🇸 Roark’sの代表値をそのまま適用し、実形状との乖離が発生
-
設計レビューで根拠不明とされ、再解析が必要に。
-
-
🇩🇪 Ktの単位系を誤り、補正応力が桁違いに
-
英単位とSI単位の混在による設計ミス。
-
-
🇫🇷 σnomの定義が曖昧で、Ktの算出根拠が不明確
-
レビューで否定される。
-
-
🇺🇸 設計資料にKtの根拠が記載されず、レビューで妥当性が否定される
-
CAE結果のみで判断され、手計算との整合が取れなかった。
-
-
🇩🇪 断面変更後にKtの再評価を行わず、設計荷重に対して耐力不足
-
設計変更がレビューに反映されず、現場で補強が必要に。
-
-
🇫🇷 Ktの適用範囲を誤解し、断面効率が低下
-
設計指針の読み違いにより、過剰設計となった。
-
-
🇺🇸 Ktの定義が設計チーム内で統一されておらず、判断基準が分裂
-
レビューで複数の補正係数が併存し、意思決定が停滞。
-
8. 工学的な歴史的背景
応力集中係数(Kt)の概念は、1913年にC.E. Inglisが切欠き周辺の応力分布を解析したことに始まります。
その後、TimoshenkoやPetersonらによって、各種形状に対するKtの代表値が体系化され、Roark’s Formulas(1938初版)に収録されました。
これにより、設計者は切欠き・段差・穴・軸肩などの形状に対して、定量的な補正係数を用いて局所応力を評価できるようになりました。
航空宇宙分野では、NASA RP-1228 や Peterson's Stress Concentration FactorsがKtの設計活用を明示し、MIL-HDBK-5Jでは金属材料の応力集中係数が規格化されています。
DIN 743-2(ドイツ)では、軸設計における切欠き形状ごとのKtが明記されており、CAE解析との整合性を取るための補正戦略として広く採用されています。
一方、日本語資料ではKtの定義や設計活用が断片的であり、CAE結果の補正にKtを用いる設計判断は未整備です。
9. 背景と課題
-
CAE解析ではKtを直接扱えないため、手計算による補正が必要
-
σmaxのメッシュ依存性が高く、Ktなしでは設計判断が過大・過小評価される
-
DIN 743-2やRoark’sの係数表が設計資料に明記されていないと、レビューで根拠が不明確になる
-
Ktの定義が設計チーム内で統一されていないと、判断基準が分裂する
-
材料の降伏応力とKt × σnomの比較が行われないと、破壊リスクが見落とされる
-
断面変更後にKtの再評価が行われないまま設計が進行し、設計限界を逸脱する事例がある
10. 設計レビューでの活用ポイント
-
Ktの定義、算出式、適用範囲を設計資料に明記する
-
σcorr = Kt × σnom を設計限界と比較し、妥当性を数値で説明する
-
Roark’s、DIN 743-2、NASA RP-1228などの係数表を根拠として提示する
-
CAE結果のσmaxに対して、Ktによる補正を行い、過大評価を防ぐ
-
設計テンプレートに代表的なKt値を組み込み、レビュー時の比較と意思決定を効率化する
-
材料選定時には、Kt × σnomが降伏応力を超えないことを確認する
-
断面変更時にはKtの再評価を必ず実施し、設計判断の透明性を維持する
出典一覧(技術資料・設計指針)
技術手法・計算式・設計支援ツール
- Roark’s Formulas for Stress and Strain(McGraw-Hill) https://jackson.engr.tamu.edu/wp-content/uploads/sites/229/2023/03/Roarks-formulas-for-stress-and-strain.pdf
- FAA-NASA Symposium on the Continued
Airworthiness of Aircraft Structures https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/13262/dot_13262_DS1.pdf
- FAA-NASA Symposium on the Continued
Airworthiness of Aircraft Structures https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/13262/dot_13262_DS1.pdf - NAFEMS – Engineering Excellence: Simulation for
Fatigue Strength and Durability - https://www.nafems.org/downloads/dropbox/nologin/fat24/fat24-proceedings.pdf?srsltid=AfmBOoq5-lsrW0CM2GnrWb_yu5C1x7twTk1ZRj6KkO-phTl2ZJxlo4oN https://www.nafems.org/publications/standards/
-
エンジニアズブック – 応力集中係数と形状補正
https://www.eng-book.com/ebw/vfs/calculation/PlasticSectionAndShapeModulus/ -
Peterson’s Stress Concentration Factors(Wiley)
形状別の応力集中係数を網羅。Roarkと並ぶ基礎資料。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119532552 https://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/532c520a9d92c.pdf
-
Roark’s Formulas for Stress and Strain
応力分布と係数表の設計補正に使用。 - NASA RP-1228 (Statistical Analysis of Fatigue Data)
実用例・設計事例
- MIT OCW – Structural Engineering Design https://ocw.mit.edu/courses/1-051-structural-engineering-design-fall-2003/ https://ocw.mit.edu/courses/1-051-structural-engineering-design-fall-2003/pages/lecture-notes/
- DIN 743-2 – Stress Concentration Factors for Undercuts
- MIL-HDBK-5J – Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA295150.pdf
工学的背景・規格
- DIN 743 – Calculation of Strength of Shaft Connections https://www.mesys.ch/doc/DIN743_CalculationBasis.pdf
- EN 1993-1-1(Eurocode 3) – Design of Steel Structures https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1993.1.1.2005.pdf
- JSME(日本機械学会)機械工学便覧 等、軸設計における応力集中係数の参照JSME(日本機械学会)機械工学便覧 等、軸設計における応力集中係数の参照
|
|
|
|
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=18574339&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6526%2F9784339046526.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f2f3626.e6b6d720.4f2f3627.c01762af/?me_id=1405859&item_id=10000405&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpierremarcolinijapan%2Fcabinet%2Fitem%2F2025%2F2510%2Fc0003_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21710612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0578%2F9784766430578_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f314f8b.664b063d.4f314f8c.138217b2/?me_id=1427774&item_id=10000016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhuggyu%2Fcabinet%2F10942442%2Fkk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=21689177&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2547%2F9784860592547_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f58377b.9432338c.4f58377c.12cd71b2/?me_id=1315222&item_id=10001406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdailymeg%2Fcabinet%2F04725073%2Ffree_1727796909176.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=18206852&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9355%2F9784820759355.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f2ead08.03ff6888.4f2ead09.4a7281cf/?me_id=1258391&item_id=10001013&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F1894ginza-sembikiya%2Fcabinet%2F04020656%2Fimgrc0116801897.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cd3468d.0c08f3fc.1cd3468e.10b04370/?me_id=1213310&item_id=20779186&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2316%2F9784339012316.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f32af93.3f76b0cc.4f32af94.a036a426/?me_id=1357996&item_id=10000173&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdining-shioso%2Fcabinet%2Fmixnuts-4_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f2cac34.c853a13e.4f2cac35.1aea3088/?me_id=1356830&item_id=10002783&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fexicoast02%2Fcabinet%2F12540646%2Fimgrc0110527089.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ce98c67.6b797ebf.1ce98c68.5e6ba467/?me_id=1278256&item_id=11560679&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0781%2F2000000130781.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f51bb1e.0a09018e.4f51bb1f.f75e9693/?me_id=1419773&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffruoats%2Fcabinet%2F09804136%2Fimgrc0095561060.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31e5074b.643365b2.31e5074c.117f1d47/?me_id=1276609&item_id=12864071&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01089%2Fbk4815810427.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4f32b31a.0e4144d9.4f32b31b.1c60c668/?me_id=1268741&item_id=10000391&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmr-mango%2Fcabinet%2Fcamangolp%2Fdaiichi%2F10070x3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)